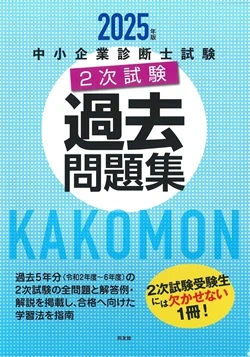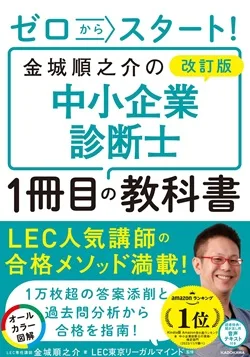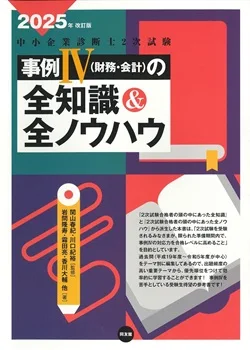Appearance
二次試験のオススメ教材
忙しい人向けまとめ
✅ 事例 Ⅰ〜Ⅲ のオススメ教材
📘 AAS 東京の解法テキスト
→ 解答の「型」を身につける。絶対に買ってほしい一冊。📘 同友館の過去問題集
→ 各予備校の解法を比較し、自分なりの改善点を整理。📘 ゼロからスタート! 金城順之介の中小企業診断士 1 冊目の教科書
→ 二次試験に必要な一次知識を図解入りでわかりやすく説明。
✅ 事例 Ⅳ のオススメ教材
- 📘 TAC よくわかる簿記シリーズ(簿記 1 級 工業簿記・原価計算 III)
→ 事例 Ⅳ より難しいので訓練効果が高い。特に 11→5→6 章の順で解く。 - 📘 同友館の過去問題集
→ 記述の「型」を定着させる。MMC 構文で安定した記述が可能に。 - 📘 事例 IV の全知識&全ノウハウ
→ 過去問 10 年分の計算問題を論点別に一気に演習できる定番書。
事例 Ⅰ〜Ⅲ の教材レビュー
🥇 第 1 位:AAS 東京公式テキスト
『中小企業診断士 2 次試験 事例問題の解法』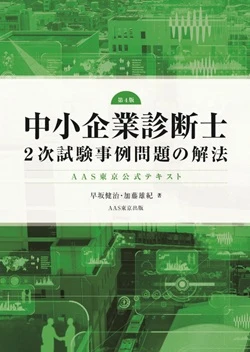 📘 Amazon リンク
📘 Amazon リンク
最重要教材。解答の“型”を身につけるならこれ一択です。
- 読むべき箇所の順序
- 与件文の左・右余白に書き込む内容
- マーキングの方法
- 答案メモの活用法
- 答案骨子の作り方
- 時間配分
などを具体的に示しています。
本書の手順通りに解き方を標準化することが、合格への最短ルートです。
🔍 補足:ふぞろいを使わなかった理由
『ふぞろい』は一切使いませんでした。理由は以下の通りです。
- キーワード偏重になりがち
- 答案を暗記してしまい、思考が止まる
- 本番では“覚えたキーワード”だけでは太刀打ちできない
キーワードの定着には役立ちますが、無理に詰め込むと読みづらい答案になるので、使うなら“補助的”に。
🥈 第 2 位:同友館『2 次試験 過去問題集』
この過去問集の特長は、複数の予備校(AAS・MMC など)が 1 事例ずつ担当して解説している点です。
- 解答アプローチや構成の“違い”を比較できる
- 自分に合う解法を選び、ノートにまとめて整理できる
- 解説が簡潔で読みやすい
🔍 補足:TAC の過去問を使わなかった理由
- 解説が長く、小説のように感じてしまう
- 要点が埋もれてしまい、効率が悪い
🥉 第 3 位:『ゼロからスタート! 金城順之介の中小企業診断士 1 冊目の教科書』
- 二次試験に必要な一次知識(戦略論、組織・人事、マーケティング・流通、生産技術、財務・会計)を図解入りで簡潔に説明
- 重要な知識のみ抜粋している
「一冊目の教科書」と表紙に記載されてますが二次試験にぴったりの本です。 文章が多くなく、図解中心なので昼休み等のスキマ時間に使いました。
🔍 補足:2 次試験合格者の頭の中にあった全知識の過去問を使わなかった理由
- とにかく文字だらけ
- 情報量が多すぎて、何が重要なのかわからない
事例 Ⅳ の教材レビュー
🥇 第 1 位:TAC『合格トレーニング 簿記 1 級 工業簿記・原価計算 III』
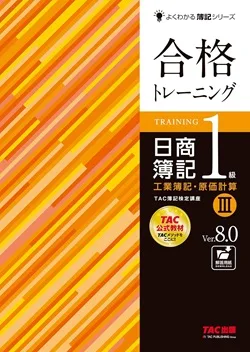 📘 公式リンク
📘 公式リンク
高得点(82 点)を取れた最大の要因です。
事例 Ⅳ より明らかに難しいので、これで訓練すれば本試験が簡単に感じます。
- 多くの受験生がミスをするであろうひっかけを用意している
- 公認会計士・税理士の受験生も使うハイレベル教材
11→5→6 章の順で学習するのが効率的。時間に余裕があれば 7 章もおすすめです(管理可能固定費の出題あり)。
🥈 第 2 位:同友館の過去問題集(再掲)
記述対策として活用。
MMC の“型”(いわゆる MMC 構文)を使えば、安定した記述が書けるようになります。
- 経営分析の第 1 問
- 最終問題の記述問題
は特に型に従って書くと時間短縮&得点源になります。
🥉 第 3 位:『事例 IV の全知識&全ノウハウ』
- 過去 10 年分の計算問題を論点別に収録(CVP、NPV など)
- 解きたい論点をまとめて演習できる
ただし、これだけでは不十分です。
試験委員は“過去問やりこみ勢”を引っかける問題を出してくるため、
全知全ノウをミスなく解けるレベルかつ 簿記 1 級レベルの教材で訓練することが重要 です。
📌 令和 4 年度以降、事例 Ⅳ の難易度が一段階上がったと感じています。
受験生同士の差をつけるために、より高度な思考力と訓練が必要です。
だからこそ、「簿記 1 級」レベルの問題集でしっかり実力をつけてください。